東京都杉並区永福町の学習塾(少人数制・個別指導)
京王井の頭線西永福駅から徒歩1分
学習支援塾すたでぃあ
夏期講習の申し込みを受け付けております。
まずは、一度お問い合わせください!
今回はやや特別支援教育よりの内容になります。
最近では、従来のWISC-IVという従来の心理検査からWISC-Vに移り変わりがあるようで、私も勉強だと思って書き記したいと思います。
WISCとは、子供向けの心理検査のことで、いわゆる認知を評価します。
認知とは、簡単に言ってしまえば脳の働きのことです。※言葉の定義を細かくするとやや難解になるので平たい表現になるのはご了承ください。
発達障害の子の場合、脳の働きに偏りがあるので、それを実際に数値化して具体的に、客観的に見てみようというのがこのWISC等の心理検査ということになります。
ここで誤った理解をしてはいけないのは、決して、数値に偏りがあるからと言って、発達障害の診断にはならない、ということです。検査結果はあくまで診断の材料になるもので、数値がこれだけだから何々という診断名となる、というわけではないのです。(ただし、IQが70未満の場合は知的障害とみなされます。)
子どもが何に困っていて、何が得意なのかを具体的に見つけるツールでもあるのでネガティブに捉えないでほしいな、と思います。
さて、前置きが長くなりました。実際のWISC-Vで測っているものを見ていきましょう。
以下の5つの言葉の指標(主要の指標)があり、この力が測られると考えると良いと思います。
①言語理解(VCI:Verval Comprehension Index)
いわゆる国語力です。ここが弱いと語彙、知識、言葉でのやりとりに苦手さを感じると思われます。
逆に、あんまり話さないな、という子がここが強い場合は、実は色々とわかっている!ということも同時に考えられます。
②視空間(VSI:Visual Spatial Index)
「見る」力です。目を使う、と言ってもいいかもしれません。ここが弱いと図形問題が苦手になることが考えられます。
また形を捉える、という点では書字にも影響が出るでしょう。
逆に強い場合、映像や視覚化の世の中ですからそういった情報を元に知識などを入力していくことは長けているかもしれません。
③流動性知能(FRI: Fluid Reasoning Index)
流動性知能と反対にある概念として結晶性知能があります。
流動性知能とは、その名の通り、新しい状況など応じて臨機応変に対応する力、つまり若い人が持っているもの。
逆に結晶性知能は長年の知識、経験がものを言う力、おじいちゃん的な感じでしょうか。
慣れない場面、状況下で行動・判断できるのか、ということがわかるかもしれません。
④ワーキングメモリー(WMI:Working Memory Index)
頭の中に情報を留めておけるのか、またそれを操作できるのか、というものです。WISC-IVからありましたが、聴覚的ワーキングメモリー、つまり耳からの情報のみでした。ところがWISC-Vでは視覚的なワーキングメモリも測られるようです。
ここが弱いとやはり学校の学習場面には非常に苦労するところです。一斉指示を聞いて「覚える」というのは集団生活では常に付きまといます。無理に覚えることを要求するのではなく、何らかのしかけ、仕組みを作って補うことが現実的だと思います。
⑤処理速度(PSI:Processing Speed Index)
簡単に言うと手先を使って作業ができるか、ということです。ここが弱いとなかなか色々なことがテキパキとできずに、遅れをとってしまいます。また全体的に、アウトプットが苦手、ということが言えそうです。アウトプットとは言葉だけに限らず、身体を使ったものも含まれると思います。
まだ私も勉強中ですが、こういった専門的なことは用語だけ聞くと難しいですし、逆に知っているとどこか自分が少し物知りになったような気分にもなります。特に英語で、何かかっこいいですし・・・苦笑
ですが、実際の子どもを目の前にした場合はいつもの行動の原因になる、本当に身近なものなのです。ですので、より目の前の子どもを見れるように知識に縛られないようにもしたいところです。
そして、よくあるのですが、数値が低いから、~ができない、という理解の結論で終わる場合が多く、それはそれで、無理に子どもを矯正することにならずにいいのですが、そこからどうするのか?ということまでを考えられるような指導者になりたいと切に思います。

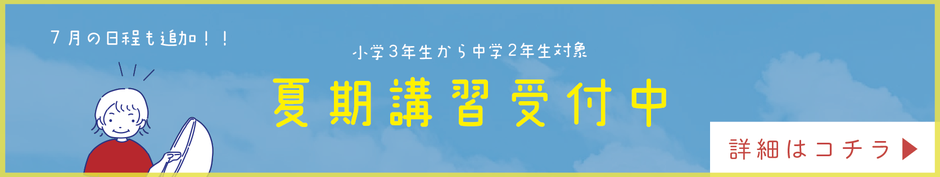
コメントをお書きください