発達障害、グレーゾーンの子への国語、算数・数学の指導は様々な教材、指導方法、知見が累積されていますが、英語についてはまだまだ足りていないのが現状だと思います。ただ、ここには英語学習の特殊性があり、その指導自体の難しさも見受けられます。
まず、英語という教科ですが、これは他の5教科のうちの4教科とは明らかに違う性質を帯びています。
英語は厳密に言えば、第二言語を習得することになります。知識を習得していくというよりも、英語という技術を学ぶことに近いものがあります。一方で英会話ではなく、あくまで英語であり、そこには文法的な知識も含まれ、非常に多元的な作りになっていると考えられます。都立入試ではスピーキングテストも導入され、その英語という教科の複雑性は年々増しています。
実際に英語を教えていて思うのは、自分が中学校時代に比べ、知識や英単語数が増えているということです。
学習指導要領を振り返ると、2002年は中学校で900単語、2012年で1200単語、2021年で1600~1800単語となっています。
つまり、この20年でおよそ倍ほどになっているのです!
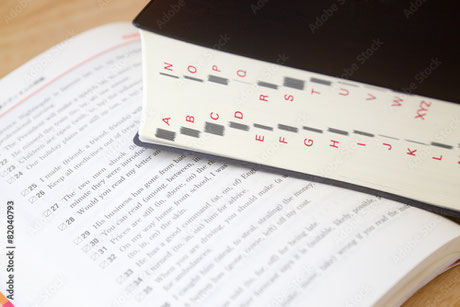
小学校からの英語が必修になっていることもありますが、そもそも学習に躓きのある発達障害(LD・ディスレクシア等)の子については、その課題の難しさは予想されるものです。
単純に単語を1日1語覚えるとしても、3年間では間に合わない計算となります。そのくらい量・質共にかなりの負担が生じることがあります。つまり、実際の現場の実感としては、定型発達の子に教えるのだけでも難しいのに、それをさらにかみ砕いて特性のある子に教えるのはその教科の構造として無理があるとしか言わざるを得ません。
さて、ではどうすればいいのか、ということになります。こういった難しさがあるという前提での話であります。
塾では、フォニックスを使っています。フォニックスはその言葉自体、知らない人もまだ多く、学校で導入されていないのが不思議なくらいです。英語圏の子どもの言葉の学習にも使われています。
フォニックスは英語の読み方の学習です。例えば、「A」は「エー」と読んでしまいますが、読み方としては「ェア」という感じ。これがA~Zまで書いてあるフォニックス表を基に、単語の学習を反復して行います。
参考までに最初の頃の英単語の小テストは、「pen」「bag」「dog」「cat」・・・と言った単語で、フォニックスの表を指さしながら文字の読み方をつなげていきます。読んでいくと何となくその単語の発音が自然と口から出てくるものを選んでいます。専門的に言えば“ブレンディング”という作業でしょうか。表を見つつ、口でそれとなく発音をしていくと、カタカナでも通用する単語ですから生徒達もピンと来て、パッと発音と意味を言うことができます。これを英語→日本語、日本語→英語の反復をし、その文字と音素をつなげていくのです。そして単語も徐々に長いもの、それまでの読み方を応用しながら読めるものに広げていきます。
英語の何が苦しいのか、それは「読めない」ということだと思います。まず読める、その上で何と書いてあるか推測する、その繰り返しによって少しずつ英文の読み、書きが習得されていきます。そのためにも、音読を大事にしています。
音読は平たい文章を何度も読む、また書く(音読筆写)を行い、頭に叩き込んでいきます。(ここについては特性に配慮しつつも音読が最も広範囲にどんな特性の子であっても一定の効果があるものと考えます)。
フォントの配慮、書きに対する配慮、とまたこちらも様々な工夫はできます。一方でどれだけ効率的にできるかも先に話を出したその分量を勘案すると重要となってきます。
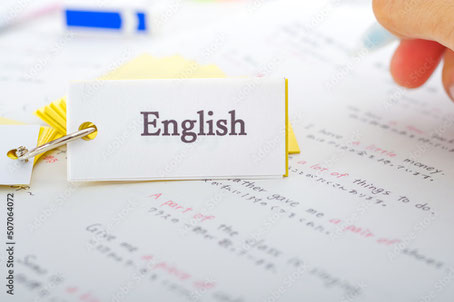
同時に教科書の内容は異文化や世界情勢を元にした文も多く、その文章のバックグラウンドとなる知識を持っているのか、持っていないかで、文章への親和性、頭に入りやすさが異なってきます。なるだけ出てきた単語は実生活でよく聞くものと関連させて話をしたり、出てくる文章の話題についても画像や動画などでできる限り具体的なイメージを持ち、その子の中での記憶に定着するようにします。最も有用なのは、日ごろから異文化、様々なことへの興味を持つことです。

英語学習は大変ですが、塾でも特性がある子でも学習ができるよう配慮をしながら指導をしています。

コメントをお書きください