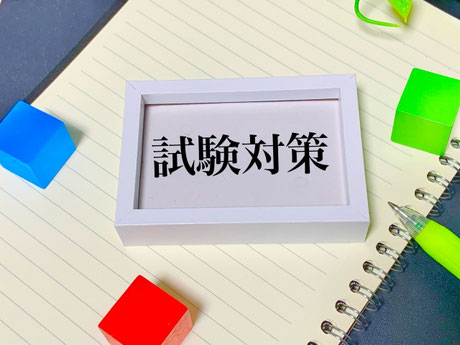
中学生のテストが返却されてきており、その問題について改めて分析をしております。
そこで、国語のテスト、特に特性のある子の場合に注目して、より実践的な対策についてを考えたいと思います。
特性にあるなしに限らず(定型発達の子も)参考になる内容と思います。
〇つまづくポイント
・難しい国語のテスト
なかなか難しいです・・・これは大人でも正解できないのでは、と思えるものも。
厳密には国語は正解がないので余計に思います。
文章自体は簡単なものであっても問いを複雑にすれば、一気に難しさが増します。
最近はなかなかワークの問題をそのまま、というわけにもいかないようです。
・問いで何が聞かれているのか。
問われていることの内容が理解できなければ解答を書くこともできません。
問いによっては、2、3行に渡って書いてあるものも多く、その文章を読み取ることも困難となります。
このあたりは、WISCにおけるワーキングメモリの数値の低さが困難につながります。
・文章が長い。
文章が長いです。問いの答えを探す時点でどこを見ればいいのかがわからなくなる可能性があります。
また教科書は挿絵などがあり、ページの感覚もあるのですが、テストでテキストを別の形で掲載されると途端に全く別のものにも感じられ、余計に読解に時間がかかることも考えられます。
・漢字が多い
覚える漢字は多いです。しかしテストに出てくる漢字は少ないです。
練習していた漢字が出てこなかったらおしまいになっていしまいます。
〇対策
・文章を頭に入れる。
初見問題は一部捨てる覚悟で、まずは教科書の文章をしっかりと頭に入れておく必要があります。
音読ができる子は音読を何回もします。音読が苦手な子はYoutubeで教科書の音声があるのでそれを聞きます。
自分で教科書の内容を諳んじて言えるくらいにします。
・問いには分かち書きを行う。
分かち書きとは、文が読みやすいように文節などで空白をつける書き方です。
これは中学生には基本適用されません。よって、自分で線で囲んでいくことをテスト勉強の中で学んでいきます。
また、何が聞かれてるのか、という核心部分を確認していき、問いの意味を考えていきます。
・どこに答えが書かれているかの見当をつける。
読解は、答えが必ず文章の中にあります。しかし、どこに書いてあるのか見当がつかなければいけません。
まず、この問いの答えはどこに書いてありそうか、という見当をつける練習をし、設問と文章中の答えの関連性を見つけていくことを念頭に置きます。
・問いの内容を絞り、問い方のバリエーションに慣れていく。
長い記述問題は捨て、よく問題集で出てくる問題について、複数の問題集を用い、問い方のバリエーションに慣れさせていきます。
・漢字は覚えられる限りで行う。
テスト範囲の漢字全てを書けることは至難の業です。できるもの、書けそうなものを選びそれをしっかりと練習をしましょう。
どうしても漢字を書くことが難しい子は漢字は捨てることも一つの選択肢です。
※中学生のテストはできることを増やすのではなく、どれだけ捨てられるかがポイントです。
テスト対策は難しいですが、できることをやっていきましょう。
すたでぃあでも対策のアイデアを生徒と一緒に考えていきます。

コメントをお書きください